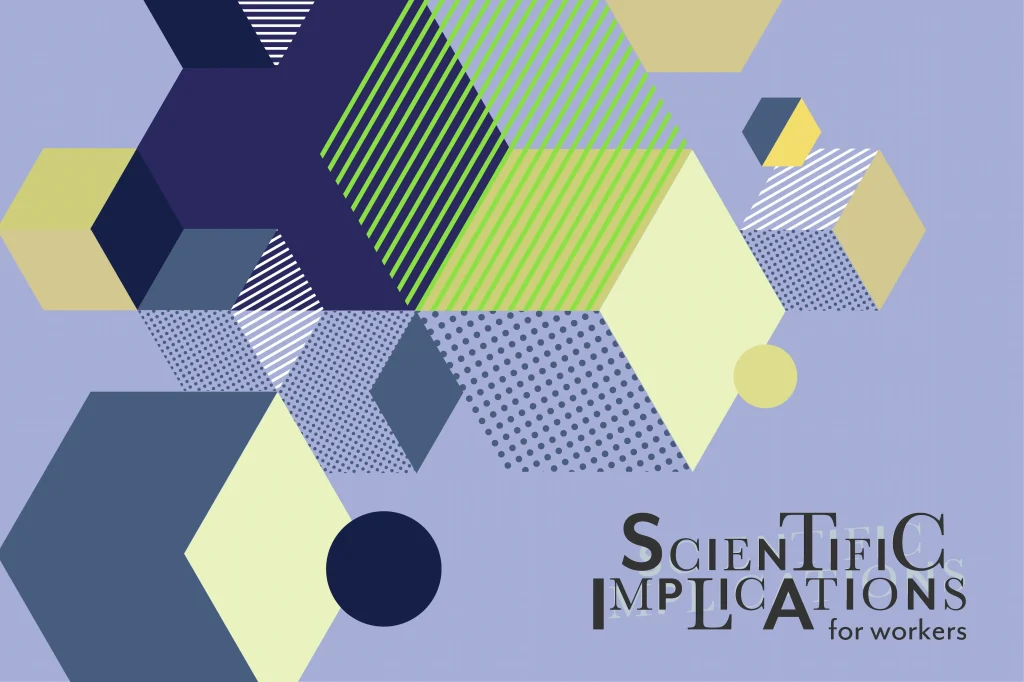仮想環境とオフィスをどう使い分ける? 組織調査のプロが語るこれからのワークプレイスの役割 | Scientific Implications

ビデオ会議やビジネスチャットなどの仮想環境とリアルなオフィスの効果的な使い分けとは? エスノグラフィーをはじめ、多角的な調査分析アプローチで企業課題と向き合う株式会社エスノグラファーの神谷俊氏にインタビューを行った。
Culture
これからのワークプレイスに欠かせない仮想環境との共存
コロナ禍をきっかけに、多くの企業でテレワークが導入され、ビデオ会議やビジネスチャットなどの「仮想環境」で仕事をする機会が増えた。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行し、オフィス回帰の機運が高まっているが、今後も仮想環境を活用したビジネスツールは引き続き使用されていくだろう。これからのワークプレイスを考えるにあたり、仮想環境の存在は無視できないものとなっている。
株式会社エスノグラファー代表取締役の神谷俊氏は、2020年4月にバーチャルワークプレイスラボを設立し、仮想環境における職場のあり方の研究を行い、その知見をもとに企業のコンサルティングを進めている。神谷氏の活動の注目すべき点は、「エスノグラフィー」と呼ばれる手法を用いて企業の組織調査を行い、課題解決に取り組んでいるところだ。
エスノグラフィーとは、もともとは文化人類学や社会学の分野で用いられてきた調査手法で、研究者が調査対象となる場に参加し、そこで生活する人々の暮らしや考え方に近接しながら、調査を進める方法論である(Van Maanen, 2011)。定量データだけでは抽出できない特有の文化や意味にアプローチする点に特異性があり、近年では組織開発やマーケティングなどに活用する企業が増えている(Morais et al., 2020)。
パンデミックから3年――。仮想環境とリアルなオフィスとの効果的な使い分けについて、エスノグラフィーを用いた調査で何が見えてきたのだろうか。神谷俊氏に話を聞いた。
 仮想環境における課題について解説する神谷氏
仮想環境における課題について解説する神谷氏
エスノグラフィーとは
組織サーベイの普及やHRテックの発展が追い風となり、組織・人事領域でデータ活用の動きが広がっている。しかし、組織やワークプレイスにおける人と環境の相互作用については、定量的に捉えることが難しい部分もある。
その実例について神谷氏は次の例を挙げた。「たとえば、組織サーベイで心理的安全性が高いという結果が得られたチームであっても、会議では誰も発言していないことがあります。背景を探ると、確かにチームメンバーは心理的安全性が高いと感じているのですが、個々のメンバーが問題意識や改善意識をもっていないために闊達な議論がされていないことがわかりました。心理的安全性だけを意識して組織開発方針を構築すると、現場の実態と乖離することがあります。現場の状況を丁寧に見定めるために、質的なアプローチを併用するケースが多いですね」。
このように、現場での参与観察やインタビュー等を通して得た、数値化できない定性的なデータを活用し、舞台裏ともいえる背景まで描き出すのが「エスノグラフィー」と呼ばれる手法だ。先述の通り、もともとは学術的な調査で使われていたが、今ではビジネスにおいても取り入れられており、神谷氏が専門とする「組織エスノグラフィー」という新たな分野も確立している。
仮想環境で生じる「二段階の課題」
神谷氏の取り組みのひとつに、「バーチャルワークプレイス研究」がある。職場環境がリアルのオフィスから、ビデオ会議やチャットをはじめとした仮想環境に移行したときに生じる問題と効果を研究するものだ。「仮想環境で仕事を行うようになったことで、同じ組織で働く人同士が空間的・時間的に分断されるという、歴史上なかった事態が起きています」と神谷氏は言う。
仮想環境で行う仕事では、各メンバーは異なる空間に存在している。また、チャットなどは非同期コミュニケーションであり、リアルタイムでの応答が期待されない前提で活用されることも多い。神谷氏は実際の調査やコンサルティングの事例から、こうした変化の渦中にある組織では次のような二段階の問題がよく起こると指摘する。
第一段階は、不確実性の問題だ。オフィスで行っていた仕事を仮想環境に移したときに発生する、「相手の状況がわからない」という問題である。仕事の優先順位をどのように捉えているのか、どのような環境で仕事をしているかといった前提をメンバー間で把握しにくくなるため、コミュニケーションや連携が思うようにいかなくなるのだ。
この課題を乗り越えるためによくとられる施策として、「業務の構造化」がある。役割分担や業務フローを明確にしたり、定量的な成果水準を定めたりして、職務内容の「見える化」を図り、密度の高いコミュニケーションがなくても仕事を進めやすくするものである。
しかし、不確実性を削減するために、過剰に構造化を進めることで、第二段階の問題が立ち現れるという。「社員の受動性が高まる」という問題だ。「一人でも進められるように業務が細分化・ルーティン化されると、今度は定められたタスクを受動的に“こなす”姿勢が強化され、コラボレーションや創造性、チームメンバーの学習レベルなどが低下してしまいます」。
オフィス環境であれば、構造化を意識的に進めなくても、適宜コミュニケーションをとりながら仕事を進めることができた。わからないことは気軽に質問したり、他者を支援したり、有機的な相互作用が自然と生じた。さらに他者との相互作用が増えれば、互いに知識を共有して学習が進んだり、互いの意見から新たなアイデアが生まれたりして、創造性が発揮されることもあった。
しかし、業務が意識的に構造化され、互いが分断された仮想環境では、そうした機会が減少する。メンバーは定められたタスクを粛々と遂行する一方で、他者との相互作用が生まれにくくなる。その結果、長期的にみるとチーム全体のパフォーマンスの低下が起こってしまうことがある。
解決の鍵となる「信頼感」と「存在感」
仮想環境におけるこうした課題は、どのように乗り越えることができるのだろうか。神谷氏は解決に向けた指針を次のように示した。「組織にはいろいろなパラドックスがありますが、コントロール(構造化) VS コラボレーション(非構造化)という図式もそのひとつです(Smith & Lewis, 2011)。この矛盾構造が示しているのは、どちらかではなく、どちらも大切であるということ。第一段階の課題に直面した組織は構造化の方向に舵を切りやすいですが、そのときに構造化一辺倒にならないようにすることが大切です」。
コントロール(構造化)とコラボレーション(非構造化)のバランスを保つためには、バーチャルチームにおける「信頼感」が鍵になるという。オンライン環境における仕事では、「姿は見えないけれど、みんな一生懸命やっているだろう」という信頼感が重要になる。この信頼感がなければ、管理者は疑心暗鬼になり、仕事を促すために構造化を進めるようになる。その帰結として、ルールや進捗スケジュール、目標などさまざまなコントロールが過剰に強化されていく。
信頼感はどうしたら高められるだろうか。当然ながら相手の人柄や考え方、仕事ぶりなどを知らないと醸成されにくい。互いに孤立した状態では信頼感は醸成しにくいため、定期的に集合し、チームのプロセスを振り返り、互いの仕事に対する向き合い方や考えを分かち合う場が求められる。「定期的にオフィスに集まって、対面でコミュニケーションをとりつつお互いの尽力を称え合う機会を設けることも、バーチャルチームでの信頼感を高めるうえでは有効だと思います」。
他方で、コラボレーションを促すためには何が求められるだろう。「人間としての存在感」を示し合い、受け止め合うことも重要と神谷氏は指摘した。「業務の構造化を進めると、メンバーそれぞれがお互いのことに無関心になりがちです。だからこそ、ソーシャルプレゼンス(相手がそこに存在しているという感覚)が求められます(Biocca et al., 2003)。オンラインだからこそ、人間らしい温かみのあるコミュニケーションを意識する必要があります」。
具体的には次のような対策が効果的だという。「相手の感情を汲み取ること、そして自分の感情を伝えることが重要です。チャット上のスタンプや、ビデオ会議での表情やジェスチャーなど些細な表現がコミュニケーションを豊かにします。また、相手の名前を呼ぶことや、自分のことを話すなど、個人として向き合っていることをコミュニケーションのなかで伝えることが有効です」。
仮想空間で生かされるリアルなオフィスの価値
これからのワークプレイスを考える切り口として、信頼感や存在感に加え、「組織文化を浸透させる」ことの重要性も神谷氏は強調する。「オンライン環境では、個々の仕事の進め方や個々の価値観がどうしても強まっていきます。つまり、個人間に“ズレ”が発生しやすくなる。そのなかでチームワークや協働環境を維持するためには、組織内で共通の価値観や認識をつくっておくことが求められます」。
また、このような“ズレ”は個人間に限った話ではないという。リモートワークでは、各チームに独自の文化(サブカルチャー)が形成されやすくなる。その一方で、組織全体が重視している文化(メインカルチャー)に触れる機会は減少する。それにより次第に、各チームにおいてサブカルチャーの影響が強くなっていく。サブカルチャーの影響力が高まりすぎると、メインカルチャーとの間に対立構造を生むリスクも高まる。会社の方針やリーダーの意見をあからさまに否定する集団が増えてしまう。これが顕著になれば、組織内の派閥化や内部分裂を招きかねない。
「こうした動きを防ぐための組織文化のメンテナンスが重要です。定期的にみんなで集まって、『自分の組織が何を大切にしているのか』を知覚し、認識を揃えることが求められます。たとえば、自社らしさを表している製品や名物リーダー、名物社員、エピソードや事例などに触れる機会や、それらを他の社員も大切に思っているのだと感じとれる機会が必要です(Deal & Kennedy, 1982)」。
このような機会はオンラインではなく、リアルな環境で設けることが重要だと神谷氏は言う。「感情や価値観が宿る情報を、伝導率高く伝えるには、やはりリアルな場が必要となります」。
たとえば、会議室でベテラン社員が看板商品のコンセプトや販売戦略について議論する様子を思い浮かべてほしい。若手社員が、間近でそれを目にすれば、ベテラン社員たちの表情や熱のこもったやり取りから自社ならではの価値観や仕事観を感じとることができるだろう。また、活躍した社員を表彰するようなイベントなども、受賞者の表情やコメント、周囲の反応から、メインカルチャーがどのようなかたちで発信され、受け止められているかという共通認識を育む機会となる。
仮想空間には、機能性や自由度の高さといったメリットがある。一方で、リアルなオフィスは信頼感の醸成や組織文化の浸透に効果を発揮する。この両面を理解し、事業の推進とコミュニティの形成がバランスよく成り立つワークプレイスを設計することが、今後ますます重要になってくるだろう。
インタビュイープロフィール
神谷 俊(かみや しゅん)
2014年法政大学大学院経営組織研究科修士課程修了。2016年に株式会社エスノグラファーを創業し、企業や地域をフィールドに活動。定量調査では見出されない人間社会の様相を紐解き、多数の組織開発・製品開発プロジェクトに貢献してきた。2020年4月に仮想環境下の「職場」を研究するバーチャルワークプレイスラボを設立。大手企業からベンチャー企業まで、数多くの企業のテレワーク移行支援を手掛け、継続的に仮想環境における組織マネジメントの知見を蓄積している。また、面白法人カヤック等の組織開発において革新的な試みを進める企業の「社外人事(外部アドバイザー)」を務めるなど、その活動は多岐にわたる。
参考文献
Biocca, F., Harms, C., & Burgoon, J. K. (2003). Toward a more robust theory and measure of social presence: Review and suggested criteria. Presence: Teleoperators & virtual environments, 12(5), 456-480.
Deal, T. E., & Kennedy, A. A. (1982). Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life. Addison-Wesley.
Morais, G. M., Santos, V. F., & Gonçalves, C. A. (2020). Netnography: Origins, foundations, evolution and axiological and methodological developments and trends. The Qualitative Report, 25(2), 441-455.
Smith, W. K., & Lewis, M. W. (2011). Toward a theory of paradox: A dynamic equilibrium model of organizing. Academy of management Review, 36(2), 381-403.
Van Maanen, J. (2011). Ethnography as work: Some rules of engagement. Journal of management studies, 48(1), 218-234.