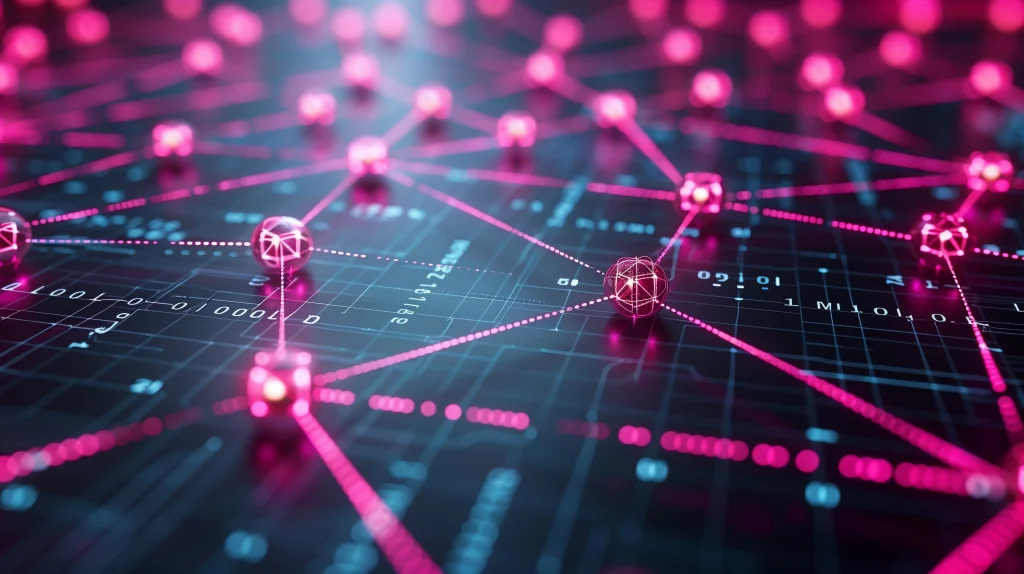米国におけるポスト・コロナ – 職場への復帰とオープンオフィスの再評価

多くの企業がオープンオフィス・モデルを採用している米国。今回は、米国の動向や浮かび上がった課題を踏まえ、ポスト・コロナのオープンオフィスの在り方について考察する。
Design
オープンオフィスとパンデミック
2020年冬現在、米国でもパンデミックの波はまだまだ鎮静化の気配を見せないが、ロックダウン規制が緩和された後の議論が喧しい。
果たして、コロナ以前のワークスタイルの復活はあるのだろうか。職場勤務が再開すれば、「物理的な空間」をどのように変えていくのか、あるいは変えていかないのかは、企業にとって喫緊の課題となるだろう。オフィスのレイアウトやデザインは、「従業員の密度」や「働く環境の雰囲気醸成」などと複雑に絡み合うものだからだ。
そうした状況を念頭に置きつつ、本記事では米国での動向を中心に見ながら、「オープンオフィス」について取り上げたい。「オープンオフィス」は、文字通り仕切りを設けず、開放感を追求したオフィスのことを指す。ブルームバーグ・シティラボのサラ・ホルダーが指摘するように、2017年のデータでは、米国の10オフィスのうち7オフィスがオープンオフィス・モデルを採用しているという。
オープンオフィス・モデルでは、「費用対効果のよさ」と「従業員同士のコラボレーションが生まれやすいこと」がメリットとされる。物理的な障壁を取り去ることで、(とりわけ異なる部署間で)豊かなコミュニケーションが生まれ、アイデアも自然発生的に生まれるというのがそこにあるロジックだ。米国では1990年代にテクノロジー企業が急増し、コラボレーションへの情熱が高まったことで、好まれるレイアウトとして確固たる地位を築いていった。
オフィスに戻りたい、しかし……
多くの企業が採用するオープンオフィスだが、パンデミック時には感染リスクが少なからず懸念される様式だと言える。そのため、今は再考するのに絶好の機会だろう。実際、人々の反応はどうだろうか。
ロックダウン以降、在宅勤務が増えたことで自分の労働環境を以前に比べてコントロールしやすくなり、なんとなく「自宅のほうが生産性が高い」と感じた人は少なくないはずだ。しかし、Genslerが米国在宅勤務調査2020で収集したデータからは、そうした考えを必ずしも一般化できないことが明らかになった。
この調査が浮き彫りにしたのは、「オフィスで働くよりも在宅で働くことを好む人たちは少数派」という結論だった。より正確には、週の大半をオフィスで仕事することを好む人が70%であるのに対し、フルタイムでの在宅勤務を好む人は調査対象者のわずか12%に過ぎなかった。
とはいえ、この結果だけを見て、コロナ後も以前と同じオフィス環境を復活させればいい、とするのは早計だ。同調査によれば、人々はオフィスの再開を願う一方、同時に「職場の変化」も期待しているという。そこに垣間見るのは、「同僚と一緒に仕事をし、何かを創造したり解決したりすることを楽しみたい」という働く人々の欲求かもしれない。コネクティビティ(つながり)は、働く人々が根源的に求めるオフィス習慣なのだ。
また、同じく2019年にGenslerが行った調査にも注目したい。コロナ前のデータだが、この時点で「ワーカーの3分の2以上(77%)が、完全にオープンな環境でも完全にプライベートな環境でもないスペースを好んでいる」ことがわかっている。オープンオフィスは長らく続くトレンドだが、「プライバシー」はある程度守りたいのだ。
この先のオープンオフィスはどうなっていくべきか、コロナ前後のこうした統計から考えさせられることは少なくない。先の見えないパンデミックに対する不安は言わずもがなだ。「健康と安全の確保」を前提に、再考していかなければならない。
米国のオープンオフィスの課題と問題点
米国の多くの企業が採用しているからといって、オープンオフィス・モデルに欠点がないわけではない。例えば、「コラボレーションの促進」がオープンオフィスの主要な目的だとされているが、実際にはこれを達成できていないと指摘する研究も少なくない。
イーサン・バーンスタインとベン・ウェーバーはハーバード・ビジネス・レビューで次のようなデータをまとめている。80年代に隆盛を極めたキュービクル型(間仕切りされた半個室)のオフィスからオープンオフィスに移行した大企業を調べたところ、対面のコミュニケーションが70%減少したことがわかっている。
また、フォーブスが収集した統計によれば、約3分の1の従業員が、オープンオフィスは生産性を低下させたり、仕事に関わる問題に対して意見するのをストップさせたりする要因になっている、と感じているという。ここに、オープンオフィスの皮肉がある。物理的な壁を取り除いても、今度は心理的な壁が立ちはだかる、というわけだ。
コロナ後のオフィス回帰を考える時、ソーシャルディスタンスとともに、こうした点を念頭に入れておくことが大切になるだろう。
米国のオフィスへの回帰 デザインの変化、トレンド、再評価
では、コロナ後のオフィス回帰で、ワーカーはどのようなトレンドや変化を期待するだろうか。あるいは、デザインは長期的な視座でどのようなソリューションを提供できるだろうか。果たして、オープンオフィスの机にただアクリル板を立てるよりも、魅力的な解決策はあるのか――。
マクロレベルでは、安全を鑑み、オフィスは「従業員の分散化」と「トラフィックの減少」に傾くだろう。多くの企業はすでに従業員のスケジュールをずらしたり、ワークステーション間のスペースを広く取ったりするなどして対応している。スケジューリングによる管理であれ、席を空けるなどの座席管理であれ、ソーシャルディスタンスの確保はオフィスを再稼働させる上で必要なステップ、というわけだ。
しかし、この「距離」(ディスタンス)は、ワーカーが慣れ親しんだオフィス文化を壊す危険性を大いに孕んでいる。オープンオフィスの再稼働には、従業員にとって安全な環境を整えながらも、同時に「コミュニティ」「コミュニケーション」「コラボレーション」の感覚を醸成するソリューションも必要だ。 パンデミック後はこのバランスが重要になってくるだろう。そのヒントを以下にいくつか取り上げたい。
1. オフィスポッドシステム「Q.workntine」

オフィスポッドシステム「Q.workntine」(画像はモハメッド・ラドワンのウェブサイトより)
パンデミックによって、1980年代に典型的だったセルラー・オフィス・プラン(個別に間仕切りしたレイアウト)への回帰を予測したくなるかもしれないが、より創造的なアプローチが求められるだろう。
その一つとして取り上げたいのが、エジプトの建築家でありデザイナーでもあるモハメッド・ラドワンが提案する「Q.workntine」だ。これは、従業員同士が接触しないように設計された、気密性の高い「オフィスの中の完全個室」。間仕切りはなく、完全に「個室化」されたポッドシステムだ。
六角形に設計され、蜂の巣状に組み合わせることができるため、省スペースにも貢献できる設計が特徴。扉はタッチレスで、パンデミックの感染リスクを極力抑える工夫がされているのも興味深い。オフィスで仕事をせざるを得ない環境に、よくフィットしそうだ。
このようなポッド型の個室を中心としたオフィス設計は、自然とその他のスペースをどのように生かすか、どのようにして従業員同士のインタラクションを生むか考えるきっかけとなるだろう。
2. ビデオチャットスペースの活用
「Q.workntine」のように完全個室型にするのではなく、別の方法でパンデミックのリスクを減らす工夫も考えられる。その一例が「Zoom Room」の採用だ。すなわち、インオフィスとリモートワーカーの組み合わせに対応した、「ビデオチャットスペース」をオフィスに追加するという発想である。
また、オフィス組と在宅組の「分散化」が進むということは、コラボレーショングループの縮小を意味する。すなわち、会議の参加人数はパンデミック以降、小さい単位になっているのではないか。これからのオープンオフィスのレイアウトでは、大会議室が少なくなり、小規模なコラボレーションスペースが増えていくことが予想される。それを象徴するのが「Zoom Room」というわけだ。
その先駆けとしてニューヨークを拠点とするRoom社の製品を取り上げたい。Room社はオフィス内に即席で置ける「電話ブース」や「スモールチーム用のディスカッションルーム」を開発する企業。パンデミック下で様々なメディアから注目を集めている。

少人数用のディスカッションルーム(画像はBUSINESS INSIDERより)
3. 新たな区画整理法、「コーナー」
最後に取り上げたいのが、「コーナー(Corner)」の概念だ。パンデミック対策、あるいはプライバシーの確保のために、閉じた部屋を用意する必要はない。2つの壁があれば(つまり「角」を作れば)、ホワイトボードやスクリーンを吊るせるだけではなく、社会的な距離感を保つための空間もプロデュースできる。「コーナー」は、その導入のしやすさから、比較的フレキシブルな対応を可能にするアプローチとも言える。
デザイナーはオフィスの優先順位を考慮し、コーナーを使ってワークスペースを有機的にゾーン整理すればいい。従業員がこれまで慣れ親しんできたオープンオフィスの開放感を維持しながら、人口密度を軽減できるプランとして、今後大いに期待できそうだ。
オフィスマネージャーやオフィスデザイナーは、どうパンデミックに向き合うか
余談だが、レイアウトとは直接関係のないデザイン面でも、デザイナーがどのような「素材」を選択するかによって、働く人たちは変化を感じられるだろう。例えば、今後は頻繁な掃除に耐え得る素材が選ばれるようになり、多孔質の素材、つまり布地のようにスプレー洗浄が難しい表面はもはや選択肢から外されることが予想される。
素材の変化に加えて、タッチレスシステムの導入なども加速するはずだ。新型コロナによる経済不況で使える予算は限られるかもしれないが、ドアの取手からコーヒーマシンまで、すべてがアプリなどで操作できるようになることが今、期待されている。
確かに、パンデミック前からオープンオフィスに対して批判があったことは事実だ。しかし、デザインの見直しがこれほど緊急に必要とされてはいなかった。今、オフィスマネージャーやオフィスデザイナーたちは、「ワーカーがどのような期待を持っているのか」、あるいは「どのような変化を望んでいるのか」を理解し、既存のオープンオフィスを活用しながら新たな課題に立ち向かっていかなければならない。