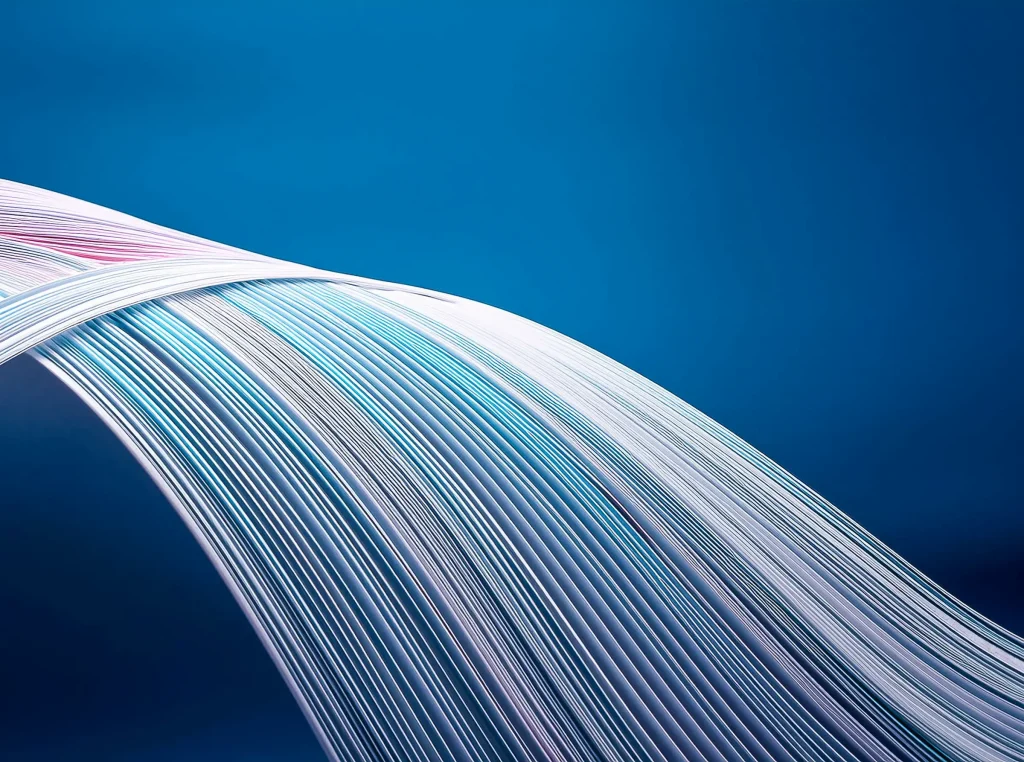オープンイノベーションの現在と未来 | 私たちは4つの課題をどう乗り越えるか
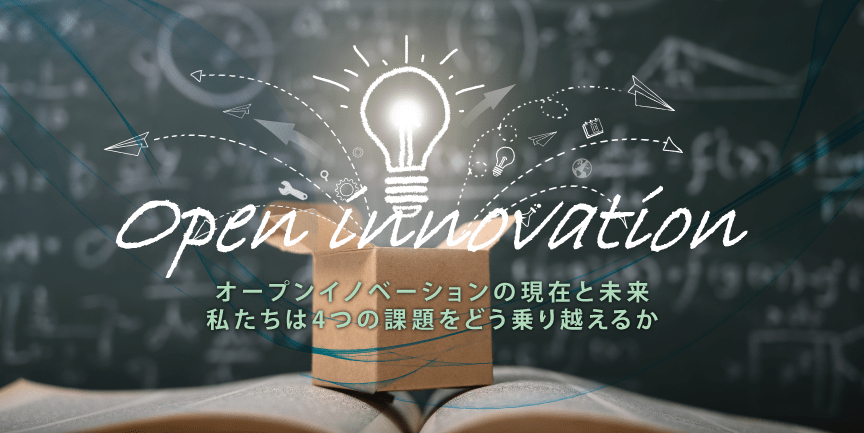
注目度が高い一方で、成功率が低いとされる「オープンイノベーション」。苦戦する日本企業の課題を整理したうえで、成功企業の事例を通してどう乗り越えるべきか考察する。
Culture
オープンイノベーションに苦戦する日本企業
企業経営において、オープンイノベーションの重要性が叫ばれるようになって久しい。オープンイノベーションとは、外部との連携で自社に足りないリソースを補完し、革新的な商品・サービスを生み出す手法だ。
従来は、自社内で完結するクローズドイノベーション、いわゆる自前主義が主流だった。しかし、時代とともに技術の移り変わりが激しくなり、商品のライフサイクルも短期化している。自前主義ではそのスピードに十分に対応できず、分野横断的な知の結合も難しいことから、オープンイノベーションへの期待が高まっている。
イノベーションというと、Apple社の「iPhone」のような、人々の価値観や生活様式を一変させる事例を連想しやすいが、必ずしも技術革新だけを指すものではない。むしろ近年は、既存の技術をベースに他業種の革新的な方法を取り込んでサービス化するなど、非技術的イノベーションが増えつつある。オープンイノベーションも、かつては「どうつくるか」という研究開発領域が中心だった。しかし今は、「どうサービス化するか」という観点でも検討されるようになり、より広範に新事業・新市場を創出する手段として重視されている。
では、実施状況についてはどうだろうか。欧米ではオープンイノベーションが活発に行われており、特に近年は大企業とスタートアップの連携が盛んだ。一方、日本国内の実施状況は、主要先進国のなかでも低水準にとどまっている。
『学習院大学経済論集』掲載の欧米企業121社、日本企業101社を対象とした調査によると、オープンイノベーションを実施したことのある欧米企業が78%なのに対し、日本企業は47%(対象は売上高250億円以上の企業が中心)。さらに、オープンイノベーションに割く予算や人員も欧米企業に比べて少ない傾向にあり、スタートアップをパートナーとする割合が低いことも同調査で浮き彫りになっている。
そこで今回は、オープンイノベーションに関する日本企業の課題を整理し、国内外の成功事例を通して解決のヒントを探りたい。
日本企業が抱える4つの課題
なぜ、多くの日本企業はオープンイノベーションに立ち遅れているのだろうか。イノベーション創出を支援する国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、2018年に『オープンイノベーション白書第2版』を発行している。これをもとに考えられるのが、以下の4つの課題だ。
1.オープンイノベーションへの理解不足
同白書の図表2-59には、オープンイノベーションの阻害要因に関するアンケート結果が掲載されている。これによると、「トップの経営層のオープン・イノベーションの必要性、目的の理解が十分でない」という回答が、オープンイノベーションが活発でない企業に目立って多い。トップをはじめ社内の理解不足があると、「オープンイノベーション活動に十分な人材や資金が配分されない」「オープンイノベーションを行うこと自体が、 戦略 ・ 目標となってしまう」といった問題が起こり得る。
2.専門組織・人材の不足
図表2-54・55では、オープンイノベーション専門の組織や人員の配置といった仕組みを整えている企業は25.5%にとどまっている。一方、整備している企業では、仕組みがうまく機能しているとの回答が過半数(59.2%)に及んだ。組織を新設せずに一時しのぎで兼任担当者を配置するなどの方法では、「十分なリソースが確保できない」「既存事業が優先されてしまう」ことにもなりかねない。
3.外部リソースを探す手段の未確立
図表2-56によると、大企業が外部連携の相手先を探すための取り組みとして最も多くあげたのは「展示会等」 (71.2%)への参加、 次いで「論文・学会情報」 (51.8%)であった。こうした従来型の手段が選ばれ、「アクセラレーションプログラム」(1.0%)、「ハッカソン・アイデアソン」(2.1%)といった新たな仕組みを活用できていない様子がうかがえる。適切な連携先を見つけるうえでは、新旧多様なネットワークの構築が欠かせないだろう。
4.連携先とのパートナーシップ構築の難しさ
前出の図表2-59では、「トップの経営層等が、技術や情報の流出のおそれがあるとの懸念を持っている」「社外との連携に係る意思決定のスピードが、円滑な連携に必要なレベルに達していない」などのパートナーシップ構築にまつわる不安も阻害要因にあげられている。費用分担や知財の取り扱い、スピード感をもった意思決定など、スムーズな連携を図れる体制もしっかり整えておく必要がある。
海外のオープンイノベーション成功事例
多くの日本企業に共通する4つの課題は、どのようにして乗り越えればよいのだろうか。そのヒントを探るため、オープンイノベーションの成功事例として知られるLEGO社の取り組みに注目したい。
デンマークの老舗玩具メーカーであるLEGO社は、多角化戦略の失敗により、1990年代後半に経営危機に陥った。ところが、その後の巻き返しにより、2016年には過去最高益を達成。業績回復の大きな要因となったのが、一般ユーザーと連携したオープンイノベーションだ。
商品に一番詳しいのはユーザーであると考え、ユーザーからアイデアを募って商品開発につなげるという新しい仕組みづくりに着手(課題1)。この新規事業を推進するにあたり、オープンイノベーション専門の部署も設置した(課題2)。具体的には、「LEGO Ideas」というWebサイトを通じてユーザーから広くアイデアを募集し(課題3)、1万票の他ユーザーの賛同を得たものは商品化を検討。商品化された際のインセンティブも設け、共創パートナーとの信頼関係を構築している(課題4)。

課題を乗り越えた国内の成功事例
前述のLEGO社は、連携相手がユーザーという特殊性はあるにせよ、4つの課題をクリアできている。これと同様に、課題を乗り越えた国内の事例について見ていきたい。
1.積水化学工業株式会社
積水化学工業の代表的な商材であるユニット住宅やパイプ、テープ、微粒子などは、1980年までに開発されたものだ。そこで、同社は2010年代前半から次の柱となる事業創出に向けてイノベーションに注力。その際、旧態依然としたR&D(Research and Development:研究開発)マネジメントが阻害要因になっていると分析し、「ビジネスモデルファースト」と「徹底したオープンイノベーション」を変革の柱に据えた(課題1)。
コーポレート部門のR&Dセンターに、 次々世代の新規事業創出というミッションを与え、2016年度には全社研究開発費342億円のうち17%に当たる55億円を配分(課題2)。また、アクセラレータープログラムの実施など、スタートアップとの共創機会も積極的につくった(課題3)
さらに、連携先とのパートナーシップ構築についても実績を残している。その一例が、「サーキュラーエコノミー」(循環経済)の実現に向けたオープンイノベーションだ。同社は米・LanzaTech社とともに、微生物を用いてゴミをエタノールに変換する技術を開発。そのエタノールを、住友化学株式会社のポリオレフィン(プラスチックの一種)製造の技術とかけ合わせて製品化する構想で、2025年度の本格事業化を目指している。必要となるリソースを求めて、国内外、企業規模を問わずパートナーシップを結び、イノベーションを実現させつつある(課題4)。
2.ソニー株式会社
「ウォークマン®」や「PlayStation®」などの開発でイノベーティブカンパニーとして知られるソニーだが、2010年頃には業績が低迷。多くの新規アイデアがありながら、事業化に至らないという課題を抱えていた。こうした状況を打破するために2014年に設立したのが、社内での新規事業を支援する専門組織「SAP(Seed Acceleration Program)」だ(課題1、2)。
この取り組みを通じて、34もの事業アイデアが育成され、14の事業が生み出された。2018年には社外からも利用できるプログラム「SSAP(Sony Startup Acceleration Program)」へと発展。参加企業に対し、アイデア出しから事業化、販売、拡大までを一貫して支援している。
SSAPの社外向け案件の第1号として誕生したのが、2021年5月に発売された子どもの仕上げ磨き専用歯ブラシ「Possi®(ポッシ)」だ。骨伝導により音楽を楽しみながら使える歯ブラシで、京セラ株式会社がSSAPを通じて、ライオン株式会社との共同開発を実現した。
社外開放することで、ソニー自身も共創パートナーと出合えるチャンスが増えている。仲介役となるケースでも、様々な分野の人脈やノウハウを社内に蓄積できるといったメリットがある(課題3)。同社のオープンイノベーションにおいて、SSAPの果たす役割は極めて大きいと言えるだろう。また、企業間で問題となりやすい知財をめぐっては、同社の知財部門などが連携することで、トラブルを未然に回避する仕組みを整えているという(課題4)。
3.株式会社資生堂
「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD(ビューティーイノベーションでよりよい世界を)」というミッションを掲げる資生堂もまた、オープンイノベーションに力を入れている。
その軸となるのが、2019年に横浜・みなとみらい地区に開設した、資生堂グローバルイノベーションセンター「S/PARK」だ。都市型オープンラボの機能を持つ同センターの狙いは「多様な知と人の融合」。ユーザーや異分野の企業などとの共創を目指し、化粧品以外のアプローチでも「ビューティー」への貢献を模索している(課題1)。
「S/PARK」では、オープンイノベーションプログラムとして「fibona」を推進(課題2)。従来の研究ドリブン型ではなく、市場や消費者に近い位置で新たな研究開発の方法を模索することを目的に、同社の研究員と外部がつながる場となっている。また、スタートアップ企業との共創を目指してパートナーを募り、2019年に3社、2021年には2社を採択。さらに海外のスタートアップ企業も1社採択し、事業化に向けたコラボレーションを進めている(課題3、4)。
4.前田建設工業株式会社 × ミツフジ株式会社
最後に、オープンイノベーションに積極的な2社が共創した事例を紹介したい。
前田建設工業は、建設市場が縮小していく今後を見据え、「脱請負」と「総合インフラサービス企業への変革」を掲げている。この変革で重視しているのが、業種を超えたオープンイノベーションだ(課題1)。
2019年に設立したICI総合センターには、様々なベンチャー企業との共創を目的に、研究・実験所としての機能が整えられている(課題2)。また、短期集中型の事業立案プログラムを開催するなど、連携・支援先の探索にも力を入れる(課題3)。
一方、西陣織の帯工場として創業したミツフジは、銀めっき繊維の導電性に注目し、2016年にウェアラブルIoTソリューション「hamon®」をリリース。生体情報データが取得できる衣類の開発とともに、データ分析技術の開発を手掛けるなど、イノベーティブな企業として異業種との連携を推進してきた(課題1)。
2社が共創に至ったのは、社会課題でもある熱中症の予知・予防を実現したいとの思いからだという。その思いが信頼関係のベースとなり、共同研究がスタート(課題4)。2021年1月には、手首につけるだけで脈波から暑熱リスクが可視化できるリストバンド型デバイス「hamon band」を発表している。
オープンイノベーションは今後、発展するか?
オープンイノベーションには数々の困難が伴い、事業化できる保証もない。仮に事業化できたとしても、既存事業のように確実な収益源となるかは不透明だ。それでも、新規事業への挑戦なくして将来の繁栄はない。その挑戦をよりスピーディーに行うには、オープンイノベーションが最適な手段となるケースは多いだろう。
今回紹介した事例においては、経営トップがオープンイノベーションの重要性を理解して戦略に落とし込み(課題1)、専門組織に人材と資金を割り当て(課題2)、最適な連携先を探索する手段を持ち(課題3)、協業にあたっては、信頼関係に根差したパートナーシップを構築している(課題4)。このように、多くの企業がつまずきやすい課題を着実にクリアしていくことが、オープンイノベーションを成功させるうえで重要と考えられる。
近年、イノベーション組織を立ち上げたり、アクセラレーションプログラムを活用したりする企業は増加傾向にある。連携先を探すWebプラットフォームや、仲介事業者による共創支援の活発化なども追い風となるだろう。日本企業におけるイノベーション創出が、今後加速するのか、あるいは減速するのか。その一つの鍵はオープンイノベーションにあるのではないだろうか。