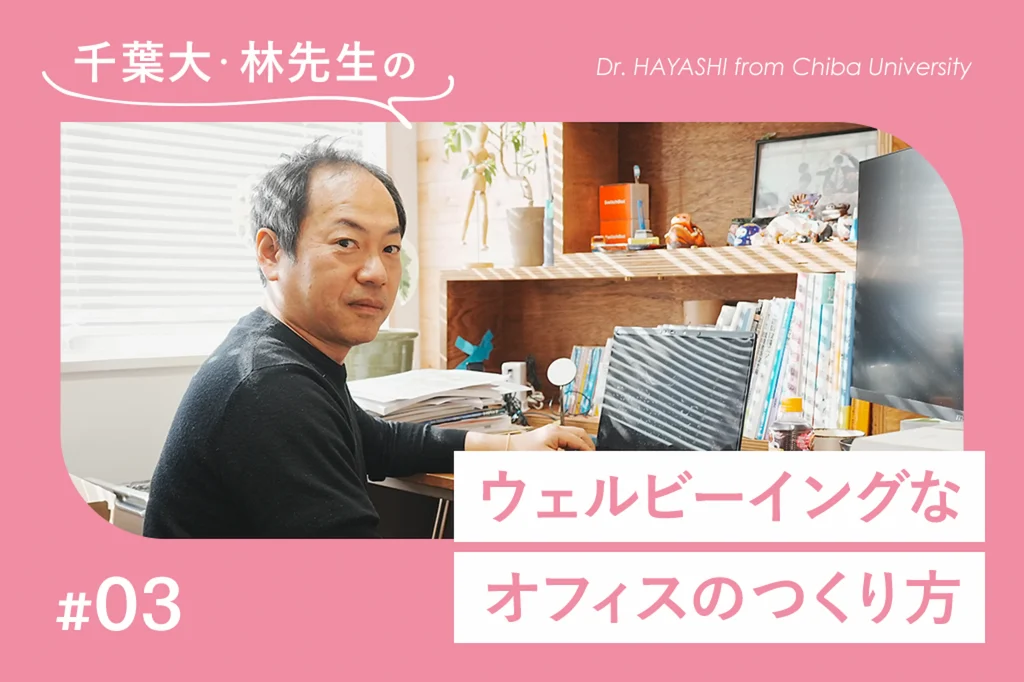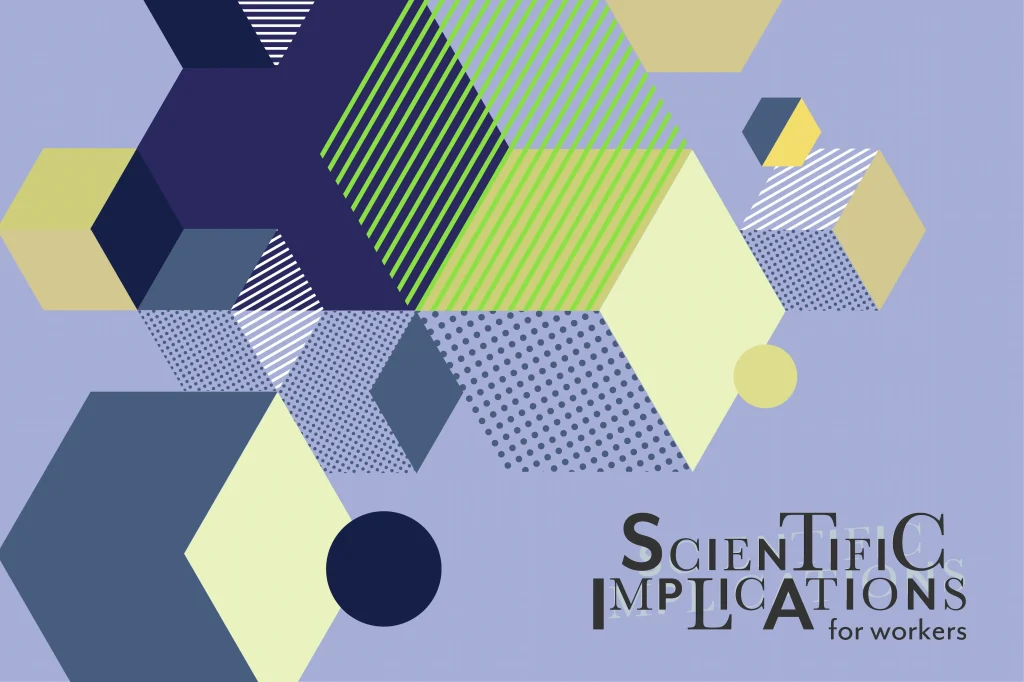実証研究から見えてきた、向社会的行動を促進する空間デザイン

職場のコミュニティは、人々が互いに礼儀正しく振る舞うことで成り立っている。研究によると、植物や鏡、香りの活用から整然とした空間の創出に至るまで、デザインは職場での良好な関係構築に効果を発揮する可能性があるという。
Design
デザインは、人がよりよい市民となるために役立つのだろうか――。研究の結果、近年注目を集めている「市民行動」を向上させる革新的な方法があることがわかってきた。
Gangl氏らがウィーンで実施した、2025年2月の『Journal of Environmental Psychology』に掲載予定の最新研究によると、自然のポスターが目に入る場所では、人はごみのポイ捨てをしにくくなるという。「ごみのポイ捨ては環境に悪影響を及ぼすものであり、社会的秩序に反するものとみなされているからだ」と研究者たちは述べている。
この研究では、ポイ捨てに対する罰金をはっきりと警告する内容のポスターを対照群として、自然のポスターの影響を検証した。その結果、自然のポスターでは客観的な清潔さは改善しなかったものの、「主観的な清潔さの体験を高めることができ、これが社会的秩序や快適さの感覚を得るための重要な推進力になりうる」ことがわかった。

「空間に投影された非言語的メッセージから、どのような組織から何を期待されているのかを学ぶ……」
ごみを捨てることより抽象度を上げると、私たちは、ある空間に示された非言語的メッセージ、例えば象徴的な意味を込めて掲示される美術作品などから、どのような組織から何を期待され、どのように行動すべきなのかを感じ取る。WestとWindの2007年の報告によると、「言葉で表現された価値観は、実際にオフィス内に具現化された価値観ほど、明確で具体的なものではない」のだという。
コミュニティがより円滑で快適に機能するために、デザインが潜在的な市民行動に果たす役割はいくつもあると調査結果は示している。

暗いより明るい、寒色より暖色で好影響
Esteky、Wooten、Bosの2020年の研究によると、より明るい空間(例えば200~300ルクスではなく1,000ルクスの場所)にいる人の方が、向社会的行動(prosocial behavior)*をとる可能性が高いことがわかった。向社会的行動とは、他者に利益をもたらす行動であり、好意的、寛大、信頼、親切、共感などが含まれる。
* 相手の利益を意図し、共感性などを伴って生起される行動で、一般に「他者の利益を意図した自発的な行動」と定義される。プロソーシャル行動、プロソーシャルビヘイビアともいう。
ChiouとChengも、2013年に同様の結果を報告している。「光と善良さには関連があることに基づき、明るさを通じて道徳的な配慮を一段と重視するようになり、倫理的に行動する可能性が高まるとの仮説を立てた。3つの実験結果はこれらの予測を裏付けるものだった」という。彼らの研究では、明るい部屋にいる参加者は、控えめな照明の部屋や薄暗い部屋にいる参加者に比べ、利己的な行動を取らなかった。また、明るい部屋の参加者は、控えめな照明の部屋の参加者よりも、より多くのデータシートのコーディングを自発的に行った。
SteidleとWerthは2014年の研究の中で、明るい空間(1,500ルクス)にいる人は、暗い空間(150ルクス)にいる人よりも有意に自制心が高いことを証明した。またWessolowski、Koenig、Schulte-Markwort、Barkmannは2014年の研究で、「職場で暖色系(寒色系とは逆)の抑えた照明を使用すると、向社会的行動が増加する」ことを発見した。

無秩序とルール違反は相関。整然とした空間が重要
2012年にChaeとZhuは、すっきりと整えられた空間とそうではない空間に人を配置して、4つの実験を行った。その結果、整理整頓された空間にいる人に比べて、「無秩序な環境に置かれている人の方が、その後に与えられたタスクの中で、衝動買い、困難な課題に対する持続力の低下、不健康な食事といった『自己統制の失敗』をより多く示す」ことがわかった。
物理的な無秩序とルール違反には密接な関係があるようだ。Kotabe、Kardan、Bermanによる2016年の研究では、視覚から得られる基本的情報が無秩序であることが、ルールに反する行動を助長する可能性は大いにあると報告されている。
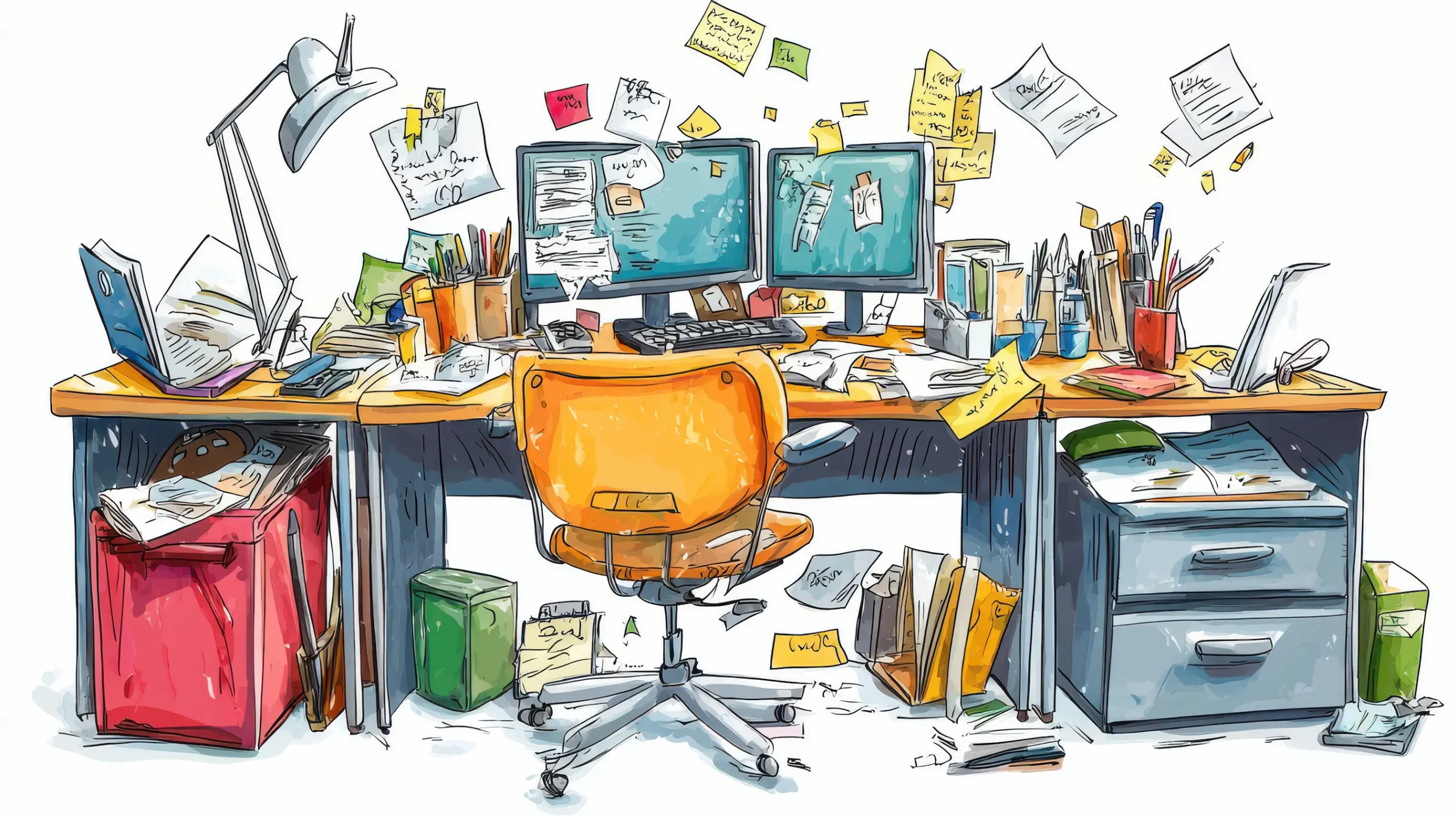
香りは道徳的な行動にも効果
2012年の研究で、De Langeと彼のチームは次のように報告している。「(オランダの)列車の客室には清掃用品の香りがほのかに広がっていた。無臭よりもクリーナーの香り(柑橘系)が漂う客室の方が、乗客が放置したごみの重量も数も少なかった」
同様に、Liljenquist、Zhong、Galinskyによる2010年の研究においても、「清潔な香りは清潔な行動を起こさせるきっかけになるだけでなく、信頼に応え慈善的な援助を行おうとする傾向を強めることで、道徳的な善行を促進する効果もある。清潔さが高潔な行動へと結びつくのは無意識的なものと思われる」と、結論付けられている。

鏡、畏敬の念、バイオフィリックデザインも向社会的行動に関連
WiekensとStapelによる2008年の研究によれば、鏡に映った自分自身を見ることで社会規範に従う可能性が高くなるという。例えば通行人が自分の姿を鏡で見ることができる場合、ポイ捨てをする可能性は低くなる(de Kort、McCalley、Middenによる2008年の研究より)。
畏敬の念と向社会的行動を結びつける調査研究も複数ある。職場での精巧な職人技や素材、壮大なスケールなどさまざまな形で、デザインは感動や驚きをもたらすことがある。JiangとSidikidesは2022年の研究で、畏敬の感情は真の自己追求を推進し、それが「より高い次元の一般的向社会性」、すなわち他者に利益をもたらす行動と結びついていることを発見した。
バイオフィリックデザインも社会規範の遵守に影響する。Bakkerとvan der Voordtは2010年、文献をレビューする中で、植物は道徳面で社会的効果をもたらす可能性があることに気付いた。
「人間は、人から見られていると感じると、より向社会的に行動するようになる……」
一方、Conty、George、Hietanenは2016年の研究で「人間は人から見られていると思うとより向社会的に行動しようとする傾向が強まり、向けられた目がポスターなどに描かれた画像の一部だったとしても変わらない」としている。少し不気味に思われた方には、こう考えてほしい――つまり、職場でのよりよい市民行動の形成に役立つデザインは、照明、鏡、植物、香りから芸術作品や秩序に至るまで、その材料には事欠かないということだ。
サリー・オーガスティン氏の最新の研究成果については、WORKTECH ACADEMYのメンバーおよびパートナー向けのInnovation Zoneで同氏が連載中のコラム「Research Roundup」を参照のこと(Innovation Zoneはこちらから)。
- 参考文献
- ・Iris Bakker and Theo van der Voordt. 2010. ‘The Influence of Plants On Productivity: A Critical Assessment of Research Findings and Test Methods.’ Facilities, vol. 28, no. 9/10, pp. 416-439.
- ・Boyoun Chae and Rui Zhu. 2012. ‘Environmental Disorder Leads to Self-Regulatory Failure.’ Proceedings, Annual Winter Conference, Society for Consumer Psychology, February 16-18, Las Vegas, pp.171-172.
- ・Wen-Bin Chiou and Ying-Yao Cheng. 2013. ‘In Broad Daylight, We Trust in God! Brightness, the Salience of Morality, and Ethical Behavior.’ Journal of Environmental Psychology, vol. 36, pp. 37-42.
- ・Laurence Conty, Nathalie George and Jari Hietanen. 2016. ‘Watching Eyes Effects: When Others Meet the Self.’ Consciousness and Cognition, vol. 45, pp. 184-197.
- ・De Lange, L. Debets, K. Ruitenburg and R. Holland. 2012. ‘Making Less of a Mess: Scent Exposure as a Tool for Behavioral Change.’ Social Influence, vol. 7, no. 2, pp. 90-97.
- ・Sina Esteky, David Wooten, and Maarten Bos. 2020. ‘Illuminating Illumination: Understanding the Influence of Ambient Lighting on Prosocial Behaviors.’ Journal of Environmental Psychology, vol. 68, 101405.
- ・Gangl, M. Seifert, P. Van Lange, and S. Pahl. ‘Nature Posters Enhance Subjective But Not Objective Cleanness in Public Housing: Evidence from a Field Experiment.’ Journal of Environmental Psychology, in press.
- ・Jiang and C. Sidikides. 2022. ‘Awe Motivates Authentic-Self Pursuit Via Self-Transcendence: Implications for Prosociality.’ Journal of Personality and Social Psychology, vol. 123, no. 3, pp. 576-596.
- ・Hiroki Kotabe, Omid Kardan, and Marc Berman. 2016. ‘The Order of Disorder: Deconstructing Visual Disorder and Its Effect on Rule-Breaking.’ Journal of Experimental Psychology: General, vol. 145, no. 12, pp. 1713-1727.
- ・Liljenquist, C. Zhong, and A. Galinsky. 2010. ‘The Smell of Virtue: Clean Scents Promote Reciprocity and Charity.’ Psychological Science, vol. 21, pp. 381-383.
- ・Anna Steidle and Lioba Werth. 2014.‘In the Spotlight: Brightness Increases Self-Awareness and Reflective Self-Regulation.’ Journal of Environmental Psychology, vol. 39, pp. 40–50.
- ・Nino Wessolowski, Heiko Koenig, Michael Schulte-Markwort, and Claus Barkmann. 2014 ‘The Effect of Variable Light on the Fidgetiness and Social Behavior of Pupils in School.’ Journal of Environmental Psychology, vol. 39, pp. 101-108.
- ・Alfred West and Yoram Wind. 2007. ‘Putting the Organization on Wheels: Workplace Design at SEI.’ California Management Review, vol. 49, no. 2, pp. 138 – 153.
- ・Carina Wiekens and Diederik Stapel. 2008. ‘The Mirror and I: When Private Opinions are in Conflict with Public Norms.’ Journal of Experimental Social Psychology, vol. 44, no. 4, pp. 1160-1166.
米シカゴに拠点を置くResearch Design Connectionsの編集長を務めるサリー・オーガスティン氏は、環境デザイン心理学の専門家。WORKTECH ACADEMYのInnovation Zoneに連載中のコラムで、仕事と職場環境に関する学術研究における最新の知見を紹介している。
※本記事は、Worker’s Resortが提携しているWORKTECH Academyの記事「Prosocial behaviour: design prompts that support citizenship」を翻訳したものです。