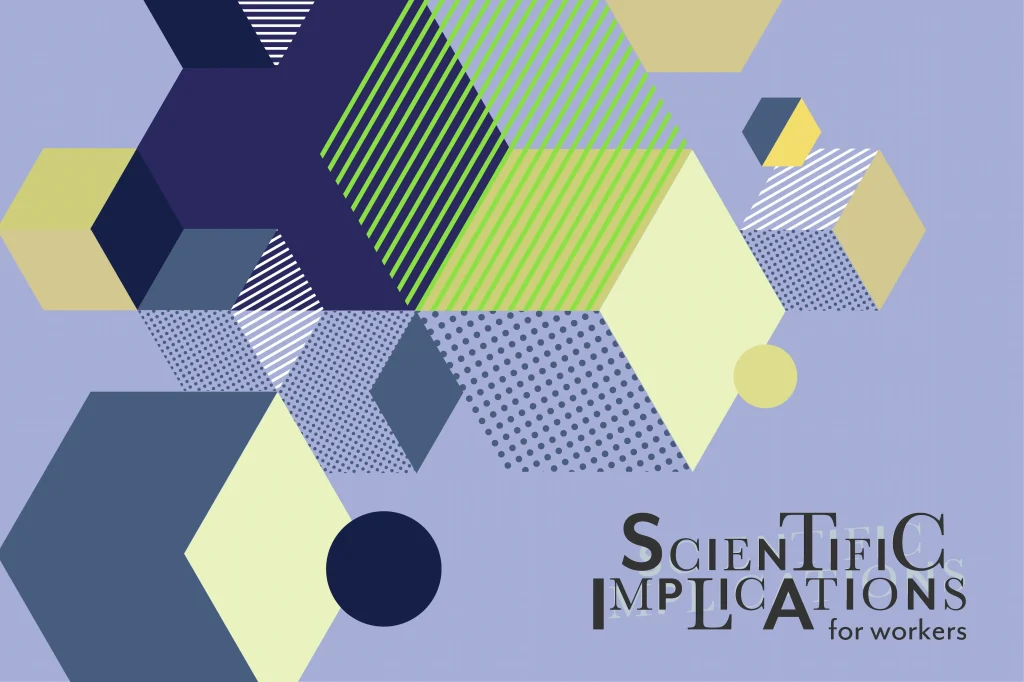「○○社の××さん」はなぜ生まれる? 「ふるまい」から考える組織と人の関係性

私たちの「ふるまい」を探る実験的プロジェクト「ビヘイビアプロジェクト」を主宰する中澤大輔さん。職場の「ふるまい」の変え方、組織や人、働く場について聞きました。
Design, Culture, Style, Research Community
社外の人とコミュニケーションを図るなかで、挨拶や話すときの態度といった相手のさりげない所作などから、その会社特有の雰囲気を感じることはないだろうか? ファッションブランドによって、スタッフの話し方や姿勢などが違うなと感じたことはないだろうか?
デザイナーでアーティストの中澤大輔さんは、そのような「人のふるまい」に着目し、国内外で精力的な活動を続けています。今回、中澤さんに、働く場や組織における「ふるまい」について聞きました。
- 中澤 大輔/なかざわ だいすけ
- デザイナー・アーティスト・物語活動家。人や場所、社会や習慣といった私たちの日常の背後に潜む小さな物語に耳を傾け、収集された物語を再構成することで、新たな物語を生み出すことに焦点を置いた活動を行っている。慶應義塾大学総合政策学部(文化人類学/建築)を卒業後、広告会社に約10年勤務、ロンドン芸術大学セントマーチンズ校修士課程(Narrative Environments)を2015年に卒業。近年では個人作家として、現代芸術作品の制作・発表を精力的に行っている。
集団になると、なぜ人の「ふるまい」が豹変するのか

――中澤さんはデザイナー、アーティスト、そして物語活動家と、3つの顔をお持ちです。
中澤 デザインの仕事は、サービスやUXのデザインに携わることが多く、アート活動は体験型の美術作品や身体表現が多いですね。デザインの仕事では削ぎ落されてしまいがちなところ、たとえば、死や悲しみとどう向き合うかみたいなことは、アートでは扱いやすい。ですから、デザインとアートの両方を行き来できる状態がちょうどいいんです。
そして、私の活動の出発点であり、デザインとアートの活動にも共通するのが、社会で生きるさまざまな人たちの行動や気持ちを観察することです。
──行動や気持ちとは、いわば人の「ふるまい」ですね。「ふるまい」に目を向けるようになったのは、なぜでしょう。
中澤 新卒で入社した広告会社で過ごした、4年間の営業経験がきっかけです。当時は広告業界に限らずどの業界でも似たところがあったと思いますが、先輩後輩といった上下関係に厳しく、高い目標を立ててそれを達成するためにモーレツに働く人たちがたくさんいました。
上司や先輩は、新人の私に対して「仕事はこうあるべき」「若手はこうあるべき」という考え方を教えます。取引先にとってベストな結果を目指すために、時には限度を超えた要求をされたり、必要以上の自己犠牲を強いられたりすることもありました。仕事に対する情熱がある余り、若手を激しく叱咤する先輩もいて、精神的に深く傷ついたこともあります。
ただ、職場では強気に振る舞っていた先輩でも、1対1で飲みに行ったりすると、意外と人間的な魅力があって「いい人」なんです。職場ではメチャメチャ怖いのに、なんだ、この人も1人の人間なんだなと感じて。このギャップはどこから来るのだろうと。
仕事となると、どうして「人間らしさ」が失われてしまうのだろう? 与えられた役割に徹するあまり、人としての優しさや配慮に欠けてしまうのはなぜだろう? ベストな結果を出すために、自らも身体や精神をすり減らして働く先輩たちの姿を見ているうちに、きっと個人の意思よりももっと強い、彼らを突き動かす何らかの社会的な「力」が働いているのではないかと考えたのです。
――確かに、社会やその場の雰囲気や空気を読んで、そこに自分の行動や態度を合わせることは珍しくないですよね。
中澤 そうなんです。みんなが空気を読みながら動いているので、1人だけで変えようと思っても改善が難しいのです。社会や組織全体の「当たり前」を変えていかない限りは、働き方も変わっていかないだろうなと。
また、時代というのも大きな要素です。私が就職した頃は、ワークライフバランスなんていう言葉なんてほとんど使われていませんでした。つまり「ふるまい」は、本人の意志が及ぶ範囲が極めて限られているもので、実はほとんど社会に操られているような状態だといってもいいでしょう。
その組織らしさを築き上げる、成り行きと意思のバランス

――日本の組織における「ふるまい」について、中澤さんはどのようにお考えでしょうか。
中澤 私は、東京、北京、ソウルの街に暮らす人々に目を向け、フィールドワークを通じて、私たちが日常何気なく行っている「ふるまい」の成り立ちとこれからを探る実験的プロジェクト「ビヘイビアプロジェクト」を2019年に立ち上げ、日中韓の6人のダンサーと共に活動を続けています。働く場における「ふるまい」も観察対象の1つで、各都市のさまざまな仕事の現場を訪れました。


あるとき、中国のダンサーが「東京の人の多くは、仕事を自分の人生の一部と捉えているようだ」という印象を話してくれました。自分の生活と仕事というものは、切り離されたもっとドライな関係で、たとえば仕事で失敗したとしても、収入が下がるなどの実害が生じない限り「まあいいか」と距離を置くことも可能です。でも、東京で働く人たちは、仕事がうまくいかないと自己否定されたような感覚や行動に陥りがちだというんです。
私はこの話を聞いたとき、最初はちょっと意外だなと思ったんですよね。日本よりもジョブ型雇用が進んだ国のほうが、役割に対する責任が明確な分、仕事のキャリアを自己と同一化しがちじゃないのかなと。しかし、専門家の話などを聞いていくと、日本では、組織に帰属するということ自体が、その人自身の存在にとって大きな意味を持つことが多いようなのです。
――もう少し詳しく教えてください。
中澤 歴史を振り返ると、日本は明治維新から第二次世界大戦までのあいだ、ナショナリズムの高まりによって、日本人であるということを強く植え付けられてきました。敗戦のショックを経て、日本社会の目標は「お国のために戦う」ことから「会社のために戦う」ことに差し替えられ、高度経済成長を迎えます。戦前は、日本という国自体が家族のようなものだと教えられてきましたが、戦後は、会社が大きな家族のような存在として扱われることになったのです。
日本がメンバーシップ型雇用だといわれるのは、こうした歴史的経緯もあって、どんな仕事をしているかより、どんな企業の一員なのかが、個人のアイデンティティに大きな影響を及ぼしてきたからではないでしょうか。
――先ほどお話しいただいた、「ふるまい」に至る経験や環境とも関係がありそうですね。その時代に生きていなかったとしても、過去の時代の習慣や環境が、今を生きる私たちにも影響を及ぼすのですね。
中澤 そうですね。そして今、日本は転換期を迎えています。グローバル経済の視点で見ると、今の日本社会や日本企業には、個人のアイデンティティを支えるだけの経済力がなくなってしまった。日本人だから、○○株式会社の社員だから、といったことだけでは幸せだと感じられなくなってしまったのです。
ただ、それは考えてみれば当たり前のことで、私たちは集団に属するという呪縛からやっと解放されつつあるのかもしれません。自分たちの社会はどうあるべきか、新たな切り口を模索しているのが、今の日本の姿だといえるでしょう。
たとえば、組織での「ふるまい」を構成するわかりやすいものの1つに「社則」や「就業規則」があります。規則というものは行動を促すための脚本や指示書のようなもので、その組織ならではの「ふるまい」と密接な関係があります。
「上司の命令は絶対だ」という規則があれば、部下は上司の意見のままに動くだろうし、「疑問をそのままにしてはいけない」という規則があれば、上司と部下の議論が生まれやすいかもしれない。形通りの規則をつくるのではなく、社員の行動を変えるようなユニークな「就業規則」を模索するのも面白そうです。
――となると、会社は従業員の「ふるまい」を設計できるということでしょうか。
中澤 理論上はそうですが、細かなところまで設計できるかというと難しいでしょう。組織は目的や計画を持って動いていますが、現場の活動というものは即興的なところが多いので、細かいところまで設計することができません。そもそも企業は、その時々の社会に必要とされた結果として成長していくものですから、そうした経緯で成立した企業という存在自体、「成り行き」によるところが多分にあるのです。
もちろん、時代の成り行きだけでなく、創業者の想いや経営層の意思、また企業で働く社員一人ひとりの想いといったものも歴史とともに積み重なり、企業のアイデンティティに反映されています。そうした人の「意思」をいかに大事にすることができるのか。企業というものの物語構造を丁寧に洞察していけば、その会社らしい「ふるまい」が編み出されていくはずです。
働き方を「ふるまい」の視点から再構築する

――その組織らしい「ふるまい」と働く場をうまく掛け合わせるために、どのような行動や意識が求められるのでしょうか。
中澤 オフィスの移転やリニューアルのためのプロジェクトに携わったことが何度かあるのですが、規模の大きい企業ほど内向きな思考になりがちです。
どんなオフィスが良いか関係者にアンケートを取ったり、社内のさまざまな部署からプロジェクトメンバーを集めてコンセプトを決めたり。それ自体が悪いわけではありませんが、どうしても既存の利害関係が反映された議論になってしまいます。結果として、せっかく環境は変わったのに社員の気質や職場の「ふるまい」は変わらないといったケースが多いようです。
では、外部の意見を取り入れればいいのかというとそうではなくて、たとえば、海外のオフィスのおしゃれなレイアウトをただ導入しただけではうまく機能しません。かっこいいオフィスにしたいという気持ちも分かるけど、大事なのは、中の視点と外の視点をうまくかけ合わせることです。組織の内と外の両方をリサーチしながら、それぞれの共通点や相違点を見出し、独自のものに転化させる「再構築」のプロセスが重要になります。
毎日朝礼を行う会社であれば、その意義について、朝の時間にやることも含めてあらためて考えてみても良いでしょう。仮に、従業員の相互理解が一番の目的であれば、朝にこだわる必要はない。皆が集まりやすい時間に実施してもいいわけです。
そうなると、午後ゆるやかに集まってコーヒーを飲みながら相互理解ができる「場」があってもいいですよね? そこで「じゃあ、コーヒータイムを大切にする北欧のオフィスのレイアウトを取り入れてみようか」という案が出てきます。単にかっこいいオフィスを真似するのではなく、自分たちのこれまでの習慣を十分理解した上で再構築することが重要なのです。
まったく新しいことを始めるよりも、これまでの文脈を踏まえながら少しずつ設計し直すことで、社員の「ふるまい」も変わりやすくなるはずです。重要なのは、観察と再構築を通じて組織としてどうありたいかという「意思」を明らかにすること。オフィスマネージャーのみなさんも、まずは、企業の過去の歴史を紐解き、今の社員の「ふるまい」をフィールドワークすることからからはじめてみてはいかがでしょうか。
本記事はリサーチコミュニティ会員限定記事です。
リサーチコミュニティとは、総務などオフィス運用やマネジメントに携わる人のみの会員制サービスです。
限定記事の閲覧のほか、各種特典もご用意しております。