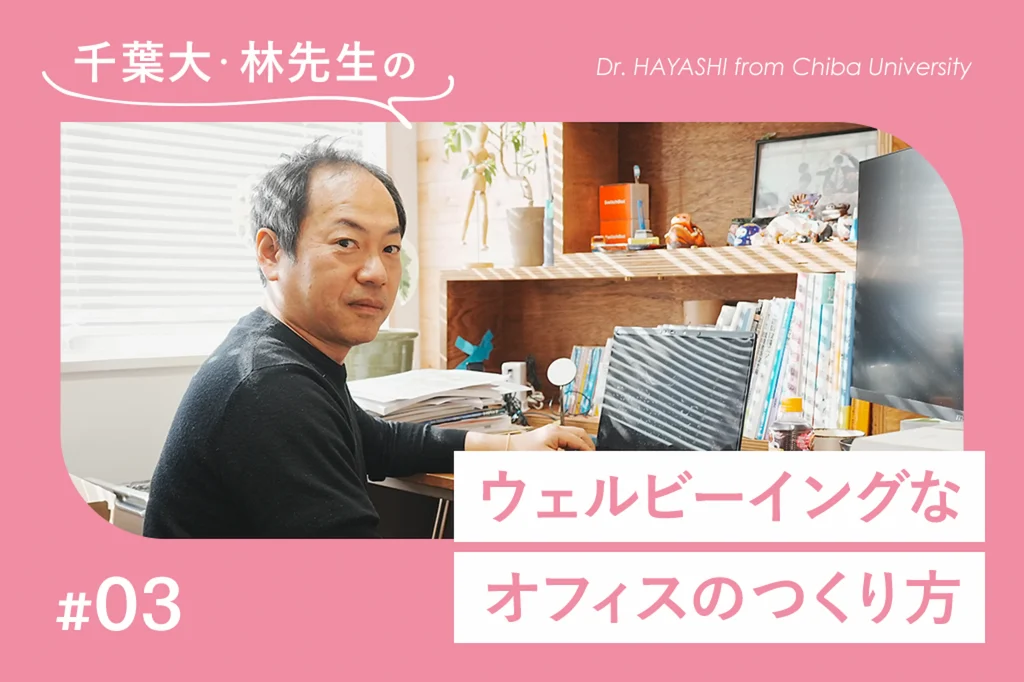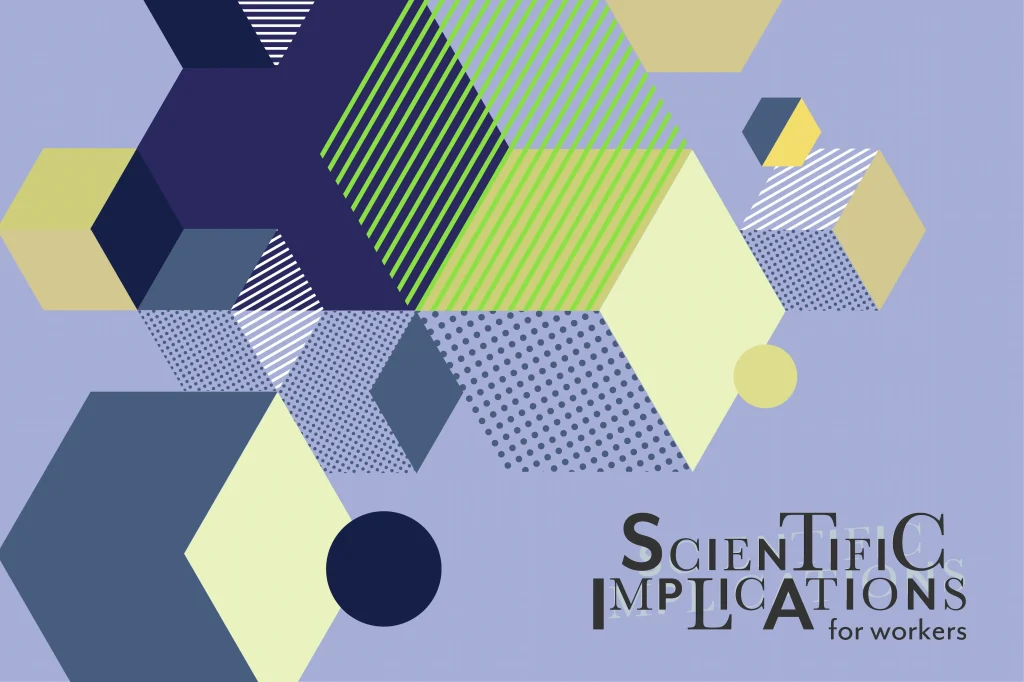リアルな現場でBAD HOPに出会った。『ルポ川崎』の著者・磯部涼さんに聞く、「現場」の多義性とコミュニティ

リモートワーク普及の反動やエンゲージメント向上への関心などから、リアルな場や人が集うことの価値にかつてないほどの関心が向けられています。社会全体でもその重要性が問い直されている「リアリティ」や「コミュニティ」は、私たちにとってどのような意味を持つのでしょうか。『ルポ川崎』『令和元年のテロリズム』を代表作とし、現場での丹念な取材から音楽シーンや社会の現実を洞察するライター・磯部涼さんへのインタビューから考えてみます。
Culture, Style, Research Community
-

磯部 涼/いそべ りょう
ライター。1978年生まれ。著書に『ヒーローはいつだって君をがっかりさせる』、『音楽が終わって、人生が始まる』、『遊びつかれた朝に』(九龍ジョーとの共著)、『ラップは何を映しているのか』(大和田俊之、吉田雅史との共著)、『ルポ川崎』、『令和元年のテロリズム』、編著などに『踊ってはいけない国、日本』、『踊ってはいけない国で、踊り続けるために』、『新しい音楽とことば』がある。
現場から得られるディテールで、人が息づく空気感を伝える
――磯部さんは音楽ライターとしての著作も豊富ですが、近年では社会現象の実態や地域コミュニティのリアルを描くルポルタージュ形式の作品が話題となっています。社会的なテーマや切り口で執筆するようになったきっかけは何だったのでしょうか?
磯部 もともとヒップホップやハードコアパンクといった、いわゆるアンダーグラウンドな音楽について書いていたのですが、面白いアーティストの中にはライブでの活動が中心でCDも出していない人も多かったんですね。インタビューをしても、一般向けのわかりやすい宣伝文句やコンセプトがはっきりとあるわけではなかったのです。
そんな彼らについて書こうとするうちに、一緒に遊んだり、生まれた街を案内してもらったりしながら、その人のこれまでの人生や、どういう場所で生活しているかという背景にも踏み込むようになったんです。
何か明確なきっかけがあったというよりは、自分を語る言葉を持たない人たちのことをどう解き明かしていくかを探る中で見つけていったのが、ルポルタージュのような手法だったのかなと思います。
――著作の中でも現地を頻繁に訪れて、関係者へのインタビューを重ねていらっしゃいますよね。現場から得ようと意識されているのはどのようなことなのでしょうか?
磯部 現場では、やはり得られる情報の量と質がまったく違います。たとえば、ライブハウスやクラブで起こっているのは何もステージの上の出来事だけではなくて、フロアで楽しんでいるのはどういう人たちなのか。あるいは寝ている人がいるかもしれないし、喧嘩をしている人たちがいるかもしれない。それらもそのイベントの雰囲気をつかむ上で重要な情報です。
音楽ライターとして活動していたときには、アーティスト名や曲順をただ並べるだけのライブ評のような記事ではなく、その場の空気感や現場感が伝わる文章を書こうと心掛けていました。それを伝えるためには、やはりディテールを細かく描写することが重要なので、意識的に情報を拾っていましたね。

――現場から得たリアリティを文章で伝えるときに心掛けているのはどのようなことでしょうか?
磯部 人がしっかりと見えるように書くことですね。ノンフィクションとして社会や地域の暗い部分にフォーカスを当てるときに人が見えないと、何となくあの地域は「やばい」「怖い」といった雰囲気だけが先行して伝わってしまう。
一見するとダークサイドになっている面でも、人によって見え方がまったく違ってくるところがとても重要です。たとえば、川崎区の工場地帯の貧困や少年の非行は社会や行政の観点では課題になるけれども、BAD HOPのようにヒップホップにのめり込んだ不良少年が東京ドーム公演を実現させるといった、その土地だからこそ育まれる文化もあるわけです。同じ現象でも誰の視点からどう見るかで解釈や意味づけが大きく変わるのがわかると、シンプルな良い/悪いという切り分けではなくなってきます。
『ルポ川崎』でも、今はホームレスだけれども日本の発展を支えていたおじいさんだったり、ヒップホップをよりどころにしている不良少年だったり、そこで暮らす人をしっかりと主人公にして、いかにカッコよく書くかを考えていましたね。
人が見えて、感情移入できるように書くためにも、やはりその場の空気を共有しているような現場のディテールを伝える必要があると思っています。
当事者意識から生まれるリアリティ
――ワークプレイスでも、リモートワークの普及からオフィス出社への揺り戻しの動きがあります。働く場面でもリアリティに価値を置く向きが強まっているように思うのですが、人がリアリティを感じるのはどのようなときだとお考えですか?
磯部 やはり当事者意識を持てたときではないでしょうか。さっきの社会や地域のダークサイドの話でもそうですが、お化け屋敷のような怖いもの見たさでちょっとのぞいてみようという人もいます。それを一概に否定するわけではないのですが、他人事として見物しようとしていた話が、実は自分の現実とつながっていると実感してもらえるような文章にすることはいつも意識していますね。
たとえば『ルポ川崎』では主に川崎区で起きた悲惨な事件や、そこで暮らす不良少年の生活を取り上げていますが、国内の工業を支えてきた工場地帯の公害問題や、いち早く移民が集まってきた地域ゆえの課題などを見ると、戦後の発展を経てきた日本の現在の縮図とも捉えられるのです。川崎区という狭い地域で起きていることが、日本社会の情勢や時代の流れを反映しているものだとわかると、同じ国や時代を生きている自分たちにも決して無関係なものではないというつながりが意識され、当事者性とリアリティが実感されるのではないでしょうか。
――ローカルな地域でのできごとが、共通の社会情勢や時代性を介して読者にリアリティをもたらすという構図は興味深いですね。
磯部 ジャンルでも場所でも、私は割となるべく狭い題材について書くようにしています。というのも、テーマが狭ければ狭いほど、そして個別具体的であればあるほど、社会と強くつながっていくという感覚があるからなんですね。「貧困」や「格差」などの大きな言葉で社会問題を語るよりも、具体的な個人の語りや経験、世界観について書くことが、取り上げたい問題について世の中に強く訴えかけられるのではないかと思っています。
――一見すると逆説的なようにも思えますが、個人にフォーカスすることで社会が浮き彫りになってくるのですね。ワークプレイスや会社の文化についての発信でも、「コミュニケーション」や「エンゲージメント」といった抽象的な言葉で表現されがちですが、実際にそこで働いている人たちの働き方や個々の語りを取り上げることでこそ見えてくる価値や存在意義がありますし、そうしたほうが納得感を伴って社内外に伝わるのだろうなと思いました。

実地だけでは完結しない、SNS時代の「現場」
――ワークプレイスに関しては、リアルとバーチャルそれぞれのメリットが指摘されますが、ノンフィクションを書くという視点だと、やはり実地の情報が重要視されるのでしょうか。
磯部 リアルな場に足を運ぶ重要性でいうと、変化に気づきやすいというのがあります。情報量が多いという話にもつながるのですが、先日久しぶりに川崎駅周辺を訪ねたら、過去にあった建物がないとか、風景がかなり変わっていたんですよね。ところが、Googleマップにはその建物がまだ残っているということもあって、インターネット上だと反映されていない。実際に行かないとわからない変化はあるのだとあらためて実感しました。
一方で、「現場」をリアルな空間だけに限定して捉えてしまうと見落としてしまう面もあります。たとえば、SNSでの記録ですね。『令和元年のテロリズム』では、事件の実態や犯人の背景を書いているのですが、当事者が亡くなっているなどの事情で実際の声を聞けないケースが結構ありました。ただ、SNS上に膨大な記録を残している人もいて、そのログをひたすら読んでいくというのも、現場を歩くような取材のひとつの形だと思うのです。
リアルとネットの二項対立というよりは、現代はありとあらゆるところに現場のようなものがあって、当然ネットにはまったく発信しない人もいますし、一方でネットにしか記録が残っていないような人もいるので、取材で使い分けていくことが必要だと感じます。
実地に足を運んでいるからとか、直接会話をしているから事実やリアルをわかっていると思い込んでしまうと、そこには慢心が生まれると思っています。
――実地での取材を丹念にされている磯部さんが、実地にリアルのすべてがあるわけではないとお話されるところに重みを感じました。ワークプレイスでもリアルオフィスだけでなく、リモート会議やチャットツールなど、さまざまなところで業務やコミュニケーションがなされているわけで、それらをすべて含めて働く人たちのリアルと捉える必要がありますね。
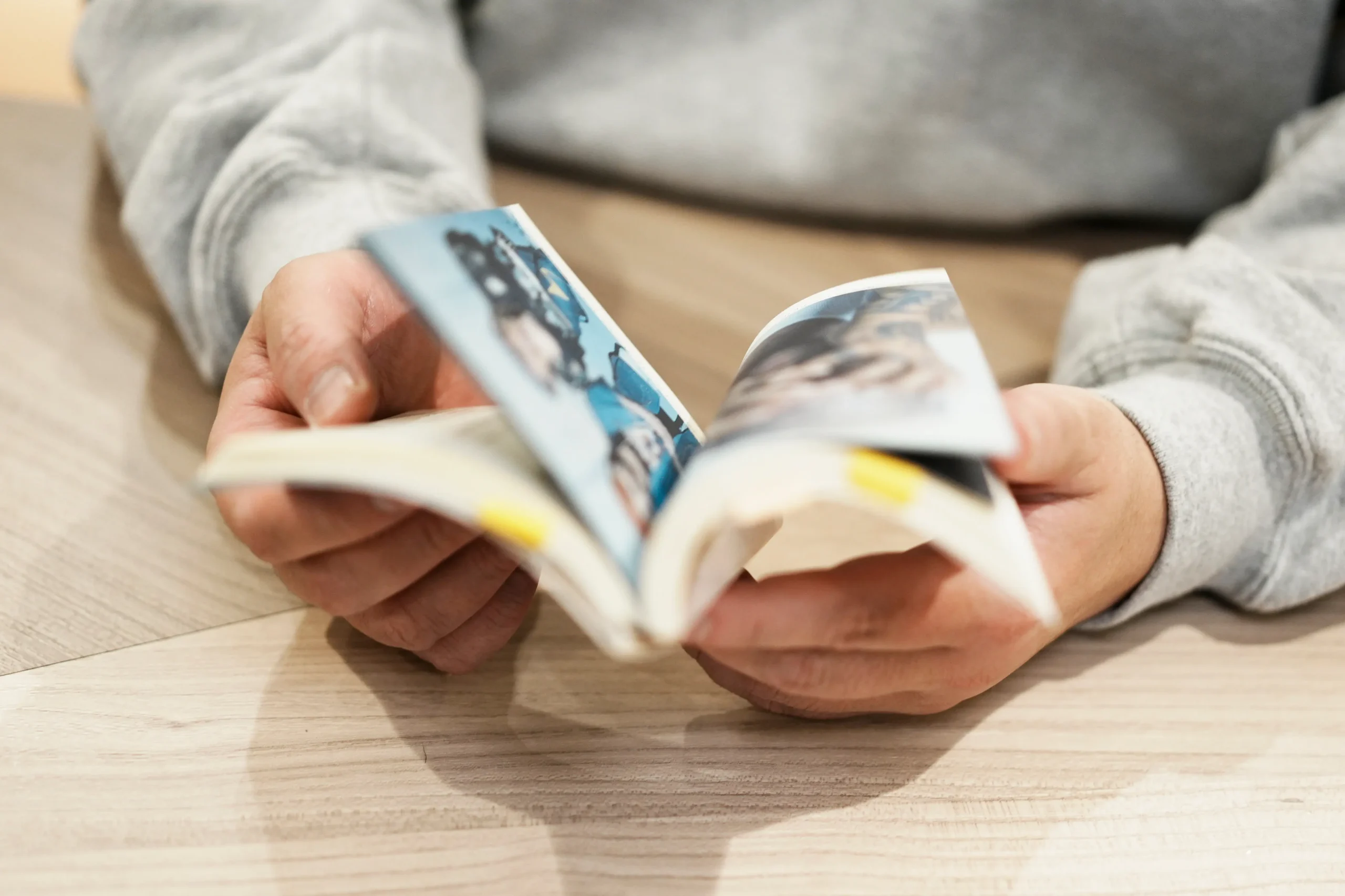
コミュニティが内包する「救い」と「しがらみ」
――会社組織や職場のチームはひとつのコミュニティと捉えられると思うのですが、地域コミュニティや音楽グループを多数取材されてきた磯部さんから見て、コミュニティとはどのようなものでしょうか?
磯部 『ルポ川崎』では、地元がセーフティネットにもなるし、しがらみにもなるという書き方をしました。いざというときに助けてくれる仲間がいるのは心強い一方で、噂がすぐに広まったり、特にアンダーグラウンドな社会では上下関係が非常に強かったりと、狭い地域ならではのしがらみに苦しさや窮屈さを感じる人もいます。
少し話がずれるのですが、最近では闇バイトの問題がよく取り上げられますよね。これは地元のしがらみとは正反対の怖さがあると思っています。地元の不良たちの間では、このグループはあの団体とつながっているから関わらないようにするといった、しがらみゆえのブレーキがあるんですよね。一方で闇バイトにはそれがなく、言われるがままにやったらいつの間にか取り返しがつかないことになっている。しがらみがいいものだと言うつもりはないのですが、結果的に一線を越えないブレーキにもなっているんですよね。
コミュニティには救いとしがらみの両方の側面があるというのは重要だと捉えています。
――最後に、これからのコミュニティについてのお考えをお聞かせください。
磯部 音楽グループなどを見ていると、コミュニティは瞬間的に立ち現れることもあれば、最初は結びついていたものがだんだんほぐれていくこともあって、継続することがなかなか難しいものだと思います。集合と離散を繰り返しながら紡がれていく性質は、会社の組織もそうかもしれません。
ただ、ひとつの固定的なコミュニティに所属しなきゃいけない、メンバーが離脱するのは許さないという考え方よりは、複数のコミュニティと柔軟につながっていく考え方のほうが楽なのではないでしょうか。
地域コミュニティで上手くいかなくなる若者を見ていると、しがらみにズブズブとはまって苦しむか、突然連絡が途絶えていなくなるかのどちらかで、すごく極端なんですよね。いなくなるというのは、しがらみからは解放される一方で、助けてくれるつながりを一切失ってしまうわけですから、それはそれで苦しいわけです。両極端のどちらかを取るつらい選択をしているのを見ると、もっとよりどころを複数持てたり、必要なときには距離を置いたり手放せたりできるような関わり方がいいのではないかと思います。
救いとしがらみのバランスを取れるような、柔軟なコミュニティの形を考えていきたいですね。

本記事はリサーチコミュニティ会員限定記事です。
リサーチコミュニティとは、総務などオフィス運用やマネジメントに携わる人のみの会員制サービスです。
限定記事の閲覧のほか、各種特典もご用意しております。